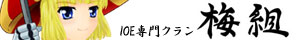おすすめリンク
イクサ仕儀記事一覧
オーストリーは弱文明?
――あせばんだ肌にくっきりと彼の手の形がのこる。にごった水のなかで呼吸しているような。身体感覚を喪失し、よどんだ神経が感覚をはこぶ。ただ、彼と抱きあった箇所だけ、それは鋭敏で、やわらかで繊細な肉がこすれあうときだけ、たしかな快感に頭の芯が花ひらくように目がさめる。だらくだ、だらくだ、間違いなくだらくだ。だけれど止めることも手放すことも自由にならない、このままふやけてお互いに肌を重ねたまま腐乱してしまえばいい、と。けれど、よくない、と頭の片隅にうかぶ呵責は、どうしても彼の求める舌に、指のうごきに、体の反応、臭い匂いに押しつぶされて跡形もない。うわごとのように、だらくしている、と私は口にする。彼はそれを聞いてわらう、おまえはかわいい、とか、なんとか。ぼくのために堕ちてよ、どこまでもどこまでも、そうしたらずっと一緒にいられるでしょ? 私は、その誘いが甘いうそだと分かっている。それでも、それを頼りにしなければ、いまの私の有様なんて、どうして肯定できる? 彼さえいれば、しあわせです。唯一の理性が、それだきっと。それが本当だから、私は彼のためにいやらしくふるまえて、堕落できて、でも狂わずに愛していられる――
オーストリーはいま、梅組内で最弱論が持ち上がっています。その筆頭は、Ethirdさんですが・・・。
とはいってもまだまだオーストリーを完全に研究できたか、といわれたら、そんなことはぜんぜんなくて、まだまだこれから、という感じが否めません。オーストリーの特性、戦術にまだまだ見えない部分があります。
いまのところオーストリーで分かっているのは、
・馬文明
・2の時代、建物(中心、塔)とグレンザーとカード長槍兵8で、だいたいカウンターが可能
以上の2点です。
それ以外のところが、よく分かっていないのです。とくに後者の2でのカウンターですが、そのあとどう続けるのか、3入り、もしくは2で追撃なのか、というところがまだ煮えきれていません。現状、そのまま3入りするのは厳しい、ということだけですね。
今回はオーストリーの馬文明という側面を掘りさげます。
■馬文明
以下のカードがあるため、かなり騎兵が強くなります。
・強化カード
1.ポーランド分割(1の時代)
ウーランのコストが肉100、金50になる。攻撃力、HP+5%
2.リピッツァー騎兵(2の時代)
ウーランの攻撃力、HP+10%
3.騎兵の戦闘力
騎兵の攻撃力、HP+15%
・生産強化カード
1.馬術訓練所
騎兵の生産速度ー40%
・変換カード
1.ハンガリー騎兵部隊(4の時代)
ウーランをハサーに変換する。
※ オーストリーの軍カードの騎兵はハサーで、使用すると1時代先のアップグレードがアクティブになり、搬送されます。
※ 4の時代のハサーカードを切るとハサーがインペリアル化され、続けてハンガリー騎兵部隊を切ることで、ウーランがすべてインペリアルハサーに変換されます。
特に注目しておきたいのは、資源コスト交換の「ポーランド分割」ではないでしょうか。
資源の収集効率が、肉と金とでは1.4倍違います。金を1取る時間で、肉は1.4取れるわけです。
コスト交換する前のウーランは、肉に換算した場合、
50+100×1.4=肉190
で1体のイメージですが、コスト変換することで、
100+50×1.4=肉170
で1体のイメージです。つまり、その分だけ少ない町のひとで生産が回るのです。
では参考程度に、もっと細かく計算してみます。
ウーランの生産スピードは35です。
資源コスト変換前のウーランを5体まわす資源は、
肉250、金500で、これを途切れなく35秒以内に資源採取するには、
肉250÷35秒=肉 7.1/秒
金500÷35秒=金14.3/秒
というレートが必要で、これはそれぞれの資源に町のひとが、
肉:8.5人 → 9人
金:23.8人 → 24人
必要です。33人集まれば、なんとか回せる、というかなり重たいコストです。
1体あたりに必要な町のひとの数は、単純に5分の1だから、肉:1.8人、金:4.8人で、6.6人です。
これを資源コスト変換することで、
肉500÷35秒=肉14.3/秒
金250÷35秒=金 7.1/秒
となり、町のひとに換算すると、
肉:17.2人 → 18人
金:11.8人 → 12人
で、必要な町のひとの数は30人です。
1体あたりに必要な町のひとの数は、単純に5分の1だから、肉:3.6人、金:2.4人で、6人です。
この差の0.6人分があとあと効いてくるわけです。
33人町のひとがいる状態で、「ポーランド分割」を切ると、町のひとが3人余剰になり、その3人が追加の資源を生産できようになります。この3人の資源生産分だけ、ウーランのコストがダウンしているとも言えるでしょう。
ということは要するに、「ポーランド分割」はウーランをコストダウンし、能力強化という結構なワザマエなカード、ということです。
このあたりのオーストリーの馬事情を理解して運用することが、オーストリーを使いこなすための一歩になるのではないか、と思います。
ただ全体的に後半よりであることが、H2Hの勝率に影響をあたえているように思います。この印象が、オーストリーが弱い、という雰囲気をましているわけで。しかし、チーム戦であれば、馬文明としてオーストリーは活躍できるのではないか、と予想しています。実践できてないのが痛いところです・・・くっ。
あと、愛すべきグレンザーの使いどころなどが研究できれば、オーストリーの戦術は見えてくるのかもなーと思っています。感覚ですが、グレンザーは十分に強いけれど、生産速度の遅さで押しきられている印象です。数を揃えるまえに相手のマスケやスカミに撃ち負ける、ということ。
だから、完全に妄想ですが、
・ウーランで前を押さえる。
・グレンザーを生産し、数を揃える。
・十分なグレンザーがそろったら、攻城と対馬をそろえて進軍する。
というシナリオが実現できたらなー、とか。