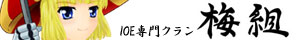おすすめリンク
イクサ仕儀記事一覧
梅組の外道達による戦術・戦略考察
アメリカの戦術 ラッシュ!
――さあ夜はこれからだ!!お楽しみはこれからだ!!ハリー!ハリーハリー!ハリーハリーハリー!
というわけで、兵は拙速を尊んだアメリカの2ラッシュを考えよう! のコーナーです。
参考リプレイはこちら。
ざっくりですが俺様理論アメリカの2入りは、3:00~4:00です。着弾は、4:30ぐらい? ワー、ネズミハヤイ! だいたい相手は2入りできていない頃合いではないでしょうか。
骨子は以下のとおりです。
◆最速の2入りを目指すために農民を生産しない。
◆最初のカードポイントは、無限でカードポイントを使わない「食料200」のため使用しない。
進化ボーナスは「前哨+金貨200」を選ぶのが安定していると思います。
この金貨200は、植民地民兵の8体分で、2入り直後に植民地民兵を5体生産するのに使用します。
さて。
アメリカの2ラッシュの特徴といえば、やっぱり内政が細くならないことでしょう。6人進化をしますが、食料200を搬送しつづけることで、肉の生産レート10/秒つまり、約農民11人分のレートを補うことができます。
つまり、
肉:11人
金貨:4人(6人の内2人を資源箱回収要員に回したから)
みたいな資源分配と同じ状況になるわけです。
アメリカの軍ユニットのコストが安いことも手伝い、この内政力でも軍ユニットを十分に出すことがきます。
あとラッシュしながら鉱夫を生産して、金貨の資源レートを底上げしていけば、いつのまにか内政も完成しているという塩梅。ラッシュは失敗すると後がないのですが、カードポイントを使用しない資源カードの存在や鉱夫の収集効率の高さなど小細工を弄することで、極端なことをしても実際、内政があまり犠牲になっておらず、なぜだか長期戦への移行も選択肢として見えてくる、と。
そんなアメリカの2ラッシュでした。
日本の戦術(第3回:騎馬戦術、Q&A)
騎馬戦術
歩兵が全力で相手を支えるあいだに
その衝突力で敵を粉砕する騎馬は剣、戦場の花形です。
騎馬の場合、その戦気を乗騎に伝えることが士気を高める上で最も重要です。
人馬一体という言葉の通り、その乗騎に闘気を伝えればOK
なにやらハッカペルの生産速度がどうとかいう記事がありますが
そのような計算は些事
たとえスイス長槍が相手でも、恐れる必要などありません。
人馬一体となり突貫踏みつぶせばいい
「薙刀騎兵、全騎突貫! 敵の数、決して多くはない」
Q&A
初回以降、歩兵、散兵、騎馬の全3兵種で終了していたのですが
読者から質問をいただきましたのでQ&Aのコーナーを・・・
Q:大砲とかはどうすれば士気が上がりますか?
A:なに?大砲? そんなものは無用です。
攻城は足軽と山伏でOK
大帝の軍略には大砲とかそんなものありません。
火矢も作ったことほとんどないし
そもそも火矢の生産拠点である城をほとんどつくりませんから、城無用
大帝と同様、孫子を軍の根幹とし「風林火山」を旗印にした
武将のなにがしも言っております。
「人は城、人は石垣、人は堀、城など無用」
日本の戦術(第2回:歩兵戦術、散兵戦術)
歩兵戦術
歩兵の役目、それは敵の攻撃を真正面から受け取め
戦列を維持、散兵の側面撃、騎兵の機動衝突が決まるまで
敵を拘束し、戦域を維持しることにあります。
いわば歩兵は盾とも言えましょう。
それは射撃戦がメインのAOE3の時代でも変わりません。
たとえ凄い数のロシアのストレレッツが相手でも問題ありません
奴らは数だけは出ますから
「足軽兵、前へ!!
騎馬突撃まで支えるだけか・・・
ふ、別に倒してしまっても構わんのだろ」
散兵戦術
世には引き撃ちというものがあるようですが、
大帝の操作量的にそんなの無理、いや無用、無用なのです。
操作量とか関係なく引きうち無用なのです。
日本の場合特に和弓で打ち初めが遅いというのもありますが
引いていると打つのが遅れる、そのため留まり打ちがこそ望ましいのです。
退がれば戦闘は長引き、その分兵は損耗するもの
踏みとどまり活路を開いてこそ王者の軍略
配下のものは皆、将の軍略からその将器、風格を見ているのです。
たとえマムルークが向かってきても、前衛を務める足軽諸氏を信じて
打ち続けましょう
「和弓兵、一斉射、その後休まず撃てえい」